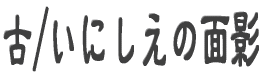 其の一阡七百弐拾
其の一阡七百弐拾怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
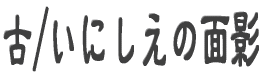 其の一阡七百弐拾
其の一阡七百弐拾
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2025年08月26日 火曜日 アップ日 2025年09月29日 月曜日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
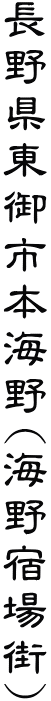 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 海野宿(うんのじゅく)は、長野県東御市本海野にある、 江戸時代における北国街道の宿場の呼称である。 現在も通りの両側に約100棟の家が連なる歴史的な町並みを形成しており、 「日本の道100選」のひとつにも選ばれている。 信濃国(信州、現:長野県)の東部、軽井沢と善光寺門前町(長野市)を 結ぶ北国街道(北国脇往還、現:国道18号旧道)の中間あたりにあった宿駅である。 もともと、平安・鎌倉時代の海野氏の領地として栄えた城下町で、 江戸時代になってから北国街道の宿場町として開設された。 現在は東御市本海野の市道田中・西海野線の一部にあり、 延長650 m、幅10 mの旧北国街道の両側には、旅籠屋造り、蚕室造り、 茅葺屋根など当時使用された約100棟の歴史的な建物が残る。 家並みの特徴は、表に格子戸がはまった家並みが続いており、 屋根に防火用の壁である「うだつ」が見られ、 2階格子の持送りや出桁(だしげた)に彫刻が施された意匠が特に目を引く。 宿場の通りの中央には、江戸時代から変わらぬ位置にある「表の川」と よばれる用水堰が流れていて、向かい合わせの家ごとに洗い場が設けられており、 江戸時代には馬に水を飲ませたり、旅行者が足を洗ったと考えられている。 (Wikipediaより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||