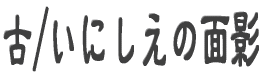 其の一阡七百壱拾九
其の一阡七百壱拾九怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
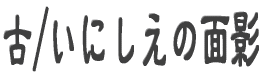 其の一阡七百壱拾九
其の一阡七百壱拾九
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2025年08月26日 火曜日 アップ日 2025年09月28日 日曜日 |
||||||||||||
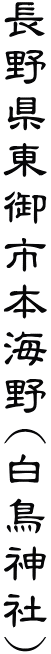 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 白鳥神社は、平安時代にこの地に鎮座していたことは、明らかである。 それは、「源平盛衰記」に記される木曽義仲挙兵のくだりによる。 義仲は、治承五年(一一八一年)海野氏を中心に白鳥河原で兵を挙げた。 この白鳥こそ白鳥大明神である。 これが史書の初出であるが、白鳥神社の創建が、いつであるかは、明確ではない。 しかし、海野の地は、奈良時代に海野郷と称し、この地から献上された品が、正倉院御物として残っている。 そんな事からも、白鳥神社の創建は、奈良から平安にかけてと推測できる。 白鳥神社は、日本武尊・貞元親王・善淵王・海野広道公の四柱を御祭神として祀っている。 日本武尊は、第十二代景行天皇の第二皇子で、西征・東征と奔走された。 この東征の帰り道に海野にご滞在になったと伝えられている。 その後、日本武尊は、伊勢の国でお亡くなりになり、白い鳥に化身される。 海野にもこの白い鳥が舞い降りる。そこで、 海野の民は、お宮を建て、日本武尊を祀った。 そして、仲哀天皇の二年、勅命により、白鳥大明神と御贈号されたと伝えられている。 貞元親王(さだやすしんのう)は、第五十六代清和天皇の第四皇子で、 眼病を患い祢津の山の湯で養生され、白鳥大明神で祈願され、平癒されたと伝えられている。 海野広道公は、海野氏の初代である。 このように、白鳥神社は、日本武尊と海野氏の祖をお祀りしているお宮である。 その後、海野氏の子孫である真田氏により、篤く尊崇を受けることとなった。 そして、真田家が松代へ移封となり、白鳥大明神を松代へ分社し、安政五年、海野神社と改称している。 (白鳥神社HPより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい) やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||