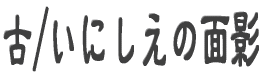 其の一阡七百壱拾二
其の一阡七百壱拾二怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
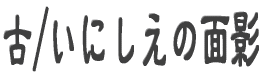 其の一阡七百壱拾二
其の一阡七百壱拾二
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2024年09月25日 水曜日 アップ日 2025年09月14日 日曜日 |
||||||||||||||||||
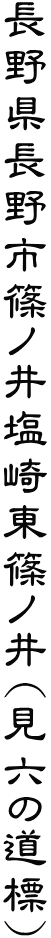 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 北国西街道(ほっこくにしかいどう)は、信濃国に存在した脇往還で、中山道と北国街道を連絡し、 松本藩や松代藩、善光寺へ向かう道のひとつとして整備された。 正しくは北国西脇往還という。現在、国土交通省では北国西往還とされている。 善光寺街道、善光寺西街道などの別名を持つ。また善光寺とは逆方向に進み、 中山道から西の伊勢や京に行く用途(伊勢参りなど)では西京街道の名が使われ、 稲荷山宿にその名が刻まれた道標が残されている。 洗馬で中山道と分かれた後、松本城下を経て山間地に入り、 街道最大の難所である猿ヶ馬場峠を超えて善光寺平の南端(稲荷山宿・桑原宿)に至り、 丹波島で北国街道に合流するのが北国西街道の正式なルートであるが、 実際に西国から善光寺に参詣する際には、十返舎一九の『続膝栗毛』に見られるように、 中山道塩尻宿から千国街道沿いに安曇野を経て、 大町宿から西山地域を超えて善光寺平の西端に至る経路も頻繁に利用された。 (Wikipediaより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||||||||