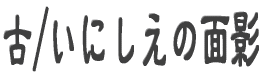 其の一阡七百壱拾
其の一阡七百壱拾怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
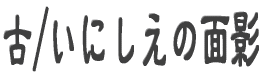 其の一阡七百壱拾
其の一阡七百壱拾
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2025年02月18日 火曜日 アップ日 2025年09月11日 木曜日 |
||||||||||||
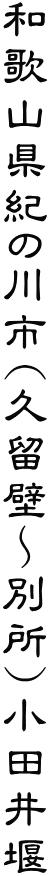 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 小田井用水 現在、紀の川の北側一帯には多くの水田が広がり、県内有数の田園地帯となっています。 しかし、かつてはたびたび干ばつに襲われ、「月夜にやける」(月夜でもかわいてしまう)と 言われるほど水の便が悪い土地でした。 転機が訪れたのは江戸時代です。現在の橋本市から岩出市まで、 紀の川の水を運ぶ大土木工事が行われたのです。紀の川北筋の農地を潤す大動脈・小田井用水の開発です。 大畑 才蔵(おおはた さいぞう、1642年(寛永19年)- 1720年(享保5年))は、 日本の農業土木技術者。江戸時代、紀州藩で、水利事業に大きな貢献をし、 小田井用水路、および藤崎井用水路の紀の川から引水した大規模かんがい用水・疏水工事を 行った人物として知られる 才蔵の主要な功績の一つである小田井は、宝永4年(1707年)に藩主吉宗の命を受けて着手した。 才蔵は、第一期、二期工事として高野口町の小田を起点として打田町にいたる 約27キロメートルの水路を施工した。 天下の暴れ川である紀の川に堰を造る(小田井堰)のは相当困難であり、出水のたびに流出した。 小田井を通すあたりは河岸段丘が出入りしており、地形が複雑で、難工事であった。 第一期工事(小田 - 那賀)は宝永5年(1708年)に、二期工事は(那賀 - 打田)は 宝永6年(1709年)に完成させた。 引き続き施工された第三期工事(打田 - 岩出)の完成には立ち会っていないようだ。 (Wikipediaより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい) やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||