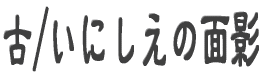 其の一阡七百三
其の一阡七百三怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
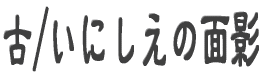 其の一阡七百三
其の一阡七百三
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2023年05月02日 火曜日 アップ日 2025年09月06日 土曜日 |
||||||||||||
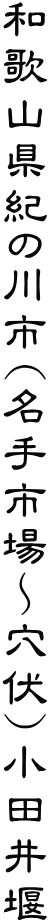 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 小田井用水 現在、紀の川の北側一帯には多くの水田が広がり、県内有数の田園地帯となっています。 しかし、かつてはたびたび干ばつに襲われ、「月夜にやける」(月夜でもかわいてしまう)と 言われるほど水の便が悪い土地でした。 転機が訪れたのは江戸時代です。現在の橋本市から岩出市まで、 紀の川の水を運ぶ大土木工事が行われたのです。紀の川北筋の農地を潤す大動脈・小田井用水の開発です。 橋本市から和歌山市に至る紀の川北岸の地域が、古くから干ばつに襲われやすかったことには理由があります。 一帯は紀の川の流れが生み出した河岸段丘で、直接水を引くには土地の標高が高く、 また溜め池だけでは水量が不足でした。 その問題を解決し、紀の川の豊かな流れを水源とする用水の開発が行われたのは元禄期です。 まずは元禄13年(1700)、藤崎井(現紀の川市藤崎)を取水口とし、 和歌山市東部に至る藤崎井用水が完成しました。 藩命により、その開削に取り組んだのは、「治水の神様」と呼ばれる大畑才蔵(おおはたさいぞう)です。 続いて宝永4年(1707)には小田井用水の開削工事を開始しました。 橋本市高野口町から紀の川市名手市場にかけての第一期工事を一年八ヶ月で完了させました。 取水口は高野口町小田です。藤崎井よりもはるか上流にあり、より複雑な地形を通す難工事でした。 (水土里ネットHPより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい) やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||