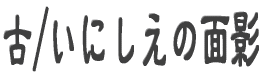 其の一阡七百六
其の一阡七百六怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
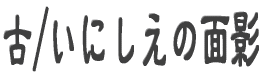 其の一阡七百六
其の一阡七百六
怪しい親爺輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
(※=マウスポインターを画像上に置いて下さい)
| 撮影日 2024年09月19日 木曜日 アップ日 2025年09月07日 日曜日 |
||||||||||||
 |
ワッカン~
資料として気になる街角 撮っておきや!(by UFO先生) 伊太祁󠄀曽神社(いたきそじんじゃ)は、 和歌山県和歌山市伊太祈曽にある神社。旧称は山東宮。 式内社(名神大社)、紀伊国一宮。旧社格は官幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。 和歌山市内にある日前神宮・國懸神宮と竈山神社、伊太祁󠄀曽神社に参詣することを「三社参り」という。 御鎮座の時期については明らかでないが、『続日本紀』の文武天皇大宝2年(702年)の記事が初見になる。 古くは現在の日前宮(日前神宮・國懸神宮)の地に祀られていたが、 垂仁天皇16年に日前神・国懸神が同所で祀られることになったので、その地を明け渡したと社伝に伝える。 その際、現在地の近くの「亥の杜」に遷座し、和銅6年(713年)に現在地に遷座したと伝えられる。 日本書紀によると、高天原を追われた素戔嗚尊とその子五十猛神は、 共に新羅に降り立つがその地を気に入ることはなく、船で出雲国に移動した。 そして素戔嗚尊は高天原から持ってきていた木の種を五十猛神に渡して日本中にその種を蒔くように命じた。 五十猛神は妹である大屋津姫命・都麻津姫命と共に九州から順番に日本中に種を蒔き始めて国中を青山にし、 最後に木の国(紀伊国)に降り立った。 このことから五十猛神は有功神(いさおしのかみ= 大変に功績のあった神様)とも呼ばれ、紀伊国に祀られることとなった。 『延喜式神名帳』では名神大社に列し、紀伊国一宮とされる。 中世には新義真言宗の根来寺と深い関係を築いていた。そのため、 神宮寺として境内南側に新義真言宗の興徳院がある他、 奥宮である丹生神社の隣には根来寺の覚鑁が伊太祁󠄀曽神社の奥之院として傳法院を建立した。 現在、興徳院は廃寺となっている。 (Wikipediaより) (※=マウスポインターを画像上に置いて下さい) やはり持ってるものはUPして
資料的に残さねば… 気を抜いたらあきません~ 何時のが出てくるか判りまへんで! 袖擦り合うも他所の縁~ いつまで知った景色が在るのやら。。 頑張ってボチボチ更新中…^^;
|
|||||||||||